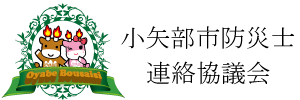DIG(ディグ)は地図から住んでいる地域の特性を知り、ハザードマップなどから被害想定を知り、災害をなるべくリアルにイメージする事で、災害時の対応を考える図上訓練と説明されています。
DIG(ディグ)を行う為の準備から説明すると、白地図をシワができないように広げて固定し、その上に透明ビニールシートをピンと張って固定し準備完了です。
DIGの進め方は、まずはシールと油性マジックで自宅などをマークします。
油性マジックで地域の環境の、道路や鉄道や川や池や避難できる場所などに、決められた色で記入します。
白地図の上に透明ビニールシートがある事で、間違えて記入しても油性マジックなので、マニキュア除光液かベンジンがあれば、消して記入し直せます。
油性マジックで地域の環境を記入し確認できたら、官公庁や医療機関や避難所などの様々な施設に、決められた色のシールを貼ります。
シールでどこにどんな施設があるのか確認できたら、更にその上に
透明ビニールシートをピンと張って固定します。
地域に合せて選んだ災害のリスクを記入しますが、その危険度を油性マジックで、色や線の太さや線の間隔で表現する事で、災害のリスクが地図上に重なった状態で確認できます。
洪水のリスクのある地域では洪水ハザードマップを使い、津波のリスクのある地域では津波ハザードマップを使い、土砂災害のリスクのある地域では土砂災害ハザードマップを使い、液状化のリスクのある地域では、国土交通省の液状化しやすさマップを使います。
記入を終えたら完成した地図を見て、地域の強みと弱みを考え話し合い、どう備えてどう対応すれば良いか相談してください。
上記の方法で完成した地図は、綺麗な仕上がりで見た目が良いのですが、当会は潤沢な予算が無く、透明ビニールシートにお金を使いたくないので、透明ビニールシートを使わない方法にしています。
その準備はテーブルが油性マジックの、インクの裏写りで汚れないように、新聞紙を2·3枚重ねて敷き固定し、その上に白地図をシワができないように広げて固定して、記入は油性マジックで直接しています。
やり直しのできない一発勝負の記入になり、せっかちな方や地元ではない方が記入すると何かしら記入ミスをしますが、のんきな方や地元の方が記入するとあまり記入ミスをしません。
あと多くの公共施設がある、市街地の地図でのDIGは良いのですが、田んぼの広がる田舎の地図でDIGをすると、環境を記入する時の道路と川以外には、記入する所やシールを貼る所が無いので、つまらないDIGになります。
こちらは透明ビニールシートを使ったDIGです。
こちらは透明ビニールシートを使わないDIGです。