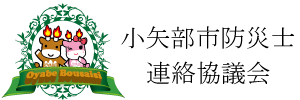今年度2回目の出前講座です。
「石動南部·中部·北部の3地区の防災会」からの依頼です。
【タイトル】
「災害への備えと避難行動と避難所」
【日時】
令和7年10月12日(日)9:30~11:15
【場所】
市民交流プラザ 1階多目的ホール
【参加者】
22名でその中に当会理事の、南部の田屋さん、中部の武部さん、北部の柴田さんも参加
【講師】
小矢部市防災士連絡協議会会長 堀内 昌樹
私は文字や数字の丸暗記がかなり苦手な為に、学業という物差しで測られると、落ちこぼれの部類に入ってしまいます。
高校生の時に実技の様な技術なら、他の人より早く理解し身につけ、すぐに応用まで考えられるという、自分の特性に気付きました。
他の人達と同じ事をしていたのでは、大勢の中に埋もれた不要な存在になってしまうので、必要な筈なのにあまり関心を持たれない事を優先する様になりました。
私がスキルアップ研修で、救助·水防·ロープワーク·搬送を行ったのは、県内の防災士で誰もそれらを行わなかったからです。
十数年前から避難所開設に関心が持たれ、コロナ禍では避難所の感染症対策に関心が持たれ、近年は避難所運営にも関心が持たれました。
しかし発災から避難所到着までの、避難行動には関心を持たれないので、今回の出前講座は避難行動を主としています。
避難行動の内容は
①地震発発生から家を出るまでにしなければいけない事
②地震発生時·発生後の徒歩や車での移動の注意点
③基本的に禁止ですが、大雨で冠水時の移動の注意点
④水没車両からの脱出方法
などです。
他には地震や洪水に対しての建物の強さ、備蓄品や在宅避難について、福祉避難所について、障害者や高齢者の避難について、家具類の転倒防止について説明しました。
台本がA4用紙11ページのボリュームでかなり幅広く説明し、地震と洪水に分けて説明しなかったので、混乱してしまわないか心配しましたが、ちゃんと理解してもらえたようです。
今回は参加者全員が大人でしたが、この内容では参加者に小学生が混ざっていた場合は、やらない方が良さそうです。