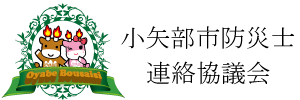「その他11の堤防被害」で説明した、「越水·深掘れ·崩壊·漏水·亀裂」の応急処置には、それぞれに適した水防工法(堤防決壊防止作業)があります。
昭和の頃ならゆっくり川の水位が上昇していたので、堤防決壊前に水防工法を完了できたかもしれませんが、現在は急激に川の水位が上昇するので、短時間で人員と資材を集めて速やかに、水防工法を完了させるのは難しく思えます。
いつ決壊するか分からない場所での作業を、仲間の消防団員にさせたくありませんし私もしたくないです。
2023(令和5)年7月の大雨では、小矢部川の堤防は決壊しませんでしたが、満水になり小矢部川支流の川や用水などから溢れる、内水氾濫などが発生しました。
この事から「その他9の田んぼダム1」で説明した、川の水位をなるべく上昇させないようにする、流域治水の考え方が有効に思えました。
大雨と地震のどちらが原因の被害か分かりませんが、令和6年秋から令和7年春まで、小矢部川の護岸の災害復旧工事が行われました。
調べるとこの場所はこれまで浸透対策がされていなかったので、この工事で遮水シートや遮水矢板などの、浸透対策もされた筈です。
ここは小矢部川河口から、30km付近の左岸の災害復旧工事でしたが、小矢部川の整備計画を見ると、ここの右岸の浸透対策工事も計画されていました。